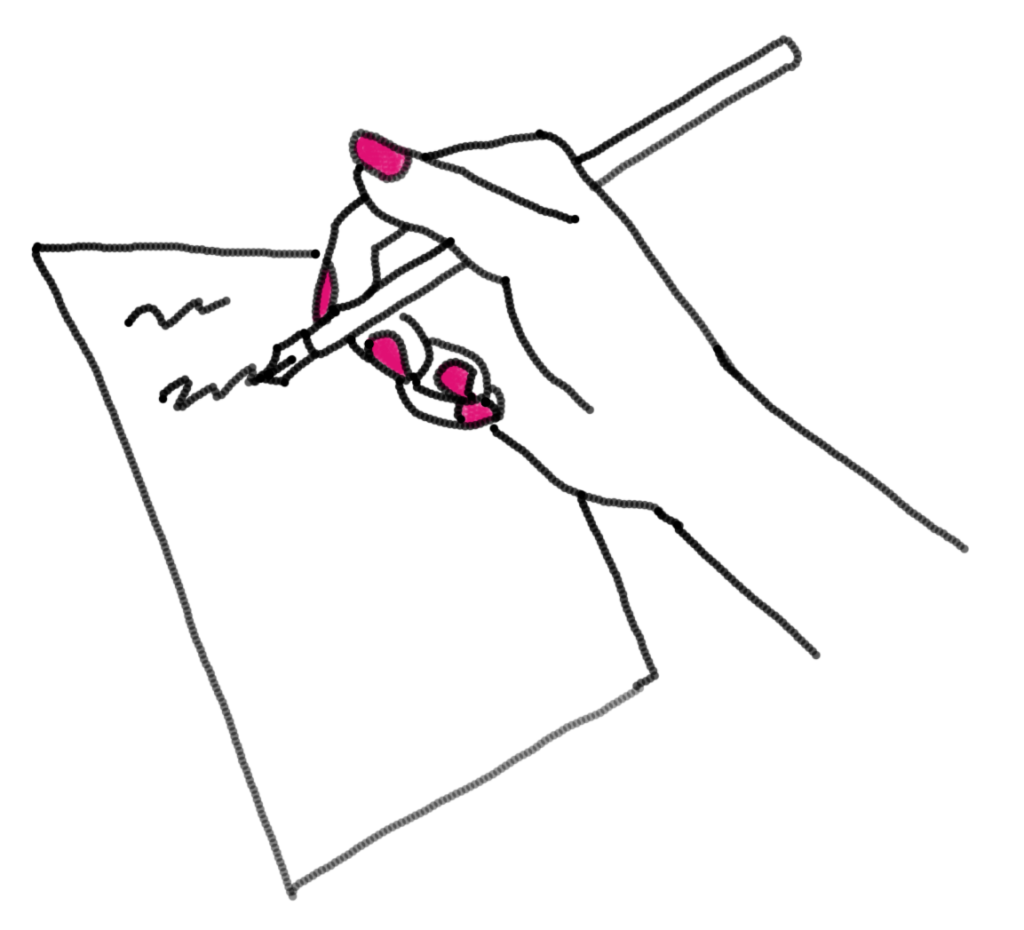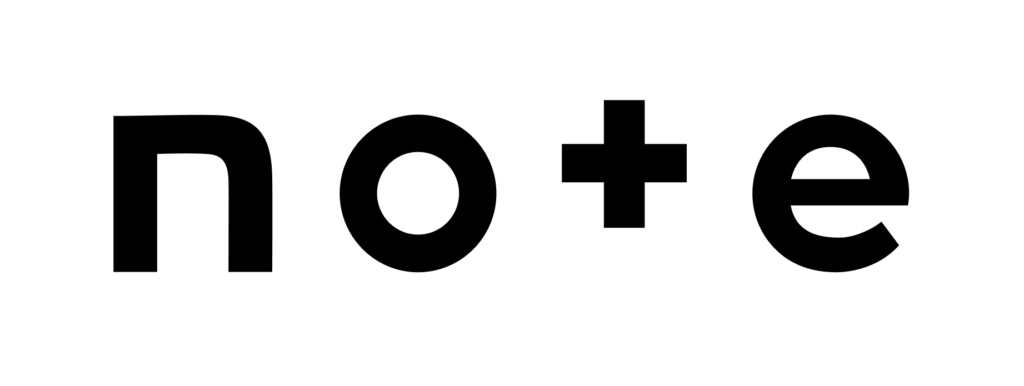露西亜料理と溜め息
先週、東京にて初めて露西亜料理のボルシチなるものを食すことがあった。
水のようにさらりとした深紅の液体の中には玉葱やキャベツなどの具が浮いており、その皿の真ん中には丸く盛った白いサワークリィムが浮かんでおり、なんだか物腰だけは柔らかい店員が「是非そのクリィムを溶かして召し上がってくださいませ」などと言うものだから、その台詞に従ってそろりそろりとスプーンで掻き混ぜてみれば液体の色は見事に鮮やかな桃色に変わりゆき、それがあまりに鮮やかな色であったが為にわたしの食欲は消え失せてしまったのだが、食してみたいと思い自ら注文したものであった為に勇気を出して口へと運んだ。
ほんの少し酸味を感じられたが、基本的にはトマト味のスープであり思ったよりも爽やかで食べやすいものであった。なるほどこれがボルシチか、と思うと同時にしかし何故にここまで料理らしからぬ色をなさるのかと疑問に思い、ボルシチの食後にいつも愛用している携帯電話で検索をかけてみたならばこのボルシチとやら、色素をわざわざ入れたスープだという。なるほどこの発色の美しさは入れられた食材本来の色などでは無く、人工的に飾られたものであるのか、なんだかこの料理を作った人間の美学を感じる。
検索結果を更に詳しく表示してみれば、この着色料を食すと人によっては尿が赤く染まることがある、と記してあるではないか。さてどういう人間は尿が赤くなり、どういう人間はならないのかを検索するほどまでの探究心は持ち合わせていなかったが故にそこで携帯電話を閉じてしまったのだが、これはかなり不思議なことを知ってしまった。なんということであろう、これは謎だ、謎でしかない。しかも時には便まで赤くなるというのだから、ボルシチという料理を食べることで人は体内に「赤色」を取り込むという不思議な体験をするのであろう。
赤色、赤色、赤色。それは情熱の色であり、血の色であり、わたしが最も好む色である。わたしの爪先はいつだって深紅の爪紅が塗られており、わたしは深紅以外の口紅を持っていない。それほどまでにわたしは赤という色を纏うのが好きなのである、赤を纏うだけでほんの少しだけ気持ちだけではあるが「いい女」になれているような気がして、ハイヒィルの似合うような気がして、童顔の自分から少し脱却出来るような気がして、何故だか何処からか自信がわいてくるのである、ああ無論勝負下着も勝負スーツもわたしは真っ赤である、要するにそれほどまでに赤色を好んでいる。
桃色ではよくない、このブログのタイトルには「ももいろ」という単語が入っているがわたしは決して桃色を特に好んでいるわけではなく、むしろ桃色の曖昧さに苛立つ時があり、どうにもこうにも特に持ち物全てを桃色にしてしまうような桃色を愛する女とは相容れないことが多いということから桃色はそこまで好きではない、好きになれない。
などなどという考え事までしていると、表面が恐ろしいほどすべすべな真ん丸の形をした露西亜風ハンバァグなる食べ物が出てきたものだから冷めぬうちに口へと運んでみればこれがまた恐ろしいほどに美味であり、わたしの短い生涯の中で最も美味しいハンバァグであったと断言出来るものであったので、こんな素敵なことはないと思わず柄にもなく写真などを撮ってしまった、そしてその味に感動し深く溜め息をついた、もはやあの溜め息は感動詞であったといえよう。
ナイフを差し込めば肉汁溢れるその様子を見ていると、なんとまあどうすればこんなにも食欲を掻き立てる料理を作ることが出来るのかとカウンター越しに見える凛とした表情をなさる男の料理人に思わず大きく敬意を表したくなる気持ちとなり、しかし怪しまれてはいけないものだから分からぬ程度に社会的に生きる術を身につけているわたしは小さくウインクをすることにしておいた。
〆に頼んだ露西亜風の紅茶にはヴァレニエというジャムのようなものが溶かされており、その甘みのなかにしっかりと生き残っている酸味を感じると最初に食したボルシチが強く思い出された。ああなるほど、露西亜料理というものはこんな食べ方や味なのだなあとどことなく幸せな感慨に浸っているとふとそろそろ店を出る時間であることに気付き、会計を済ませる直前にお手洗いへと向かい用を足し髪型を整えて、その小さなビルの地下にある小さな露西亜料理屋をあとにした。
店を出て、御茶ノ水の空気を胸いっぱいに吸い、雪の降る日であったものだから肺を冷たくて気持ちのよい空気でいっぱいに満たし、明治大学の巨大な建物を背後に見ながら数歩歩いたところで、先ほど尿の色を確認するのを忘れたことに気づき、わたしは大きく溜め息をついた。