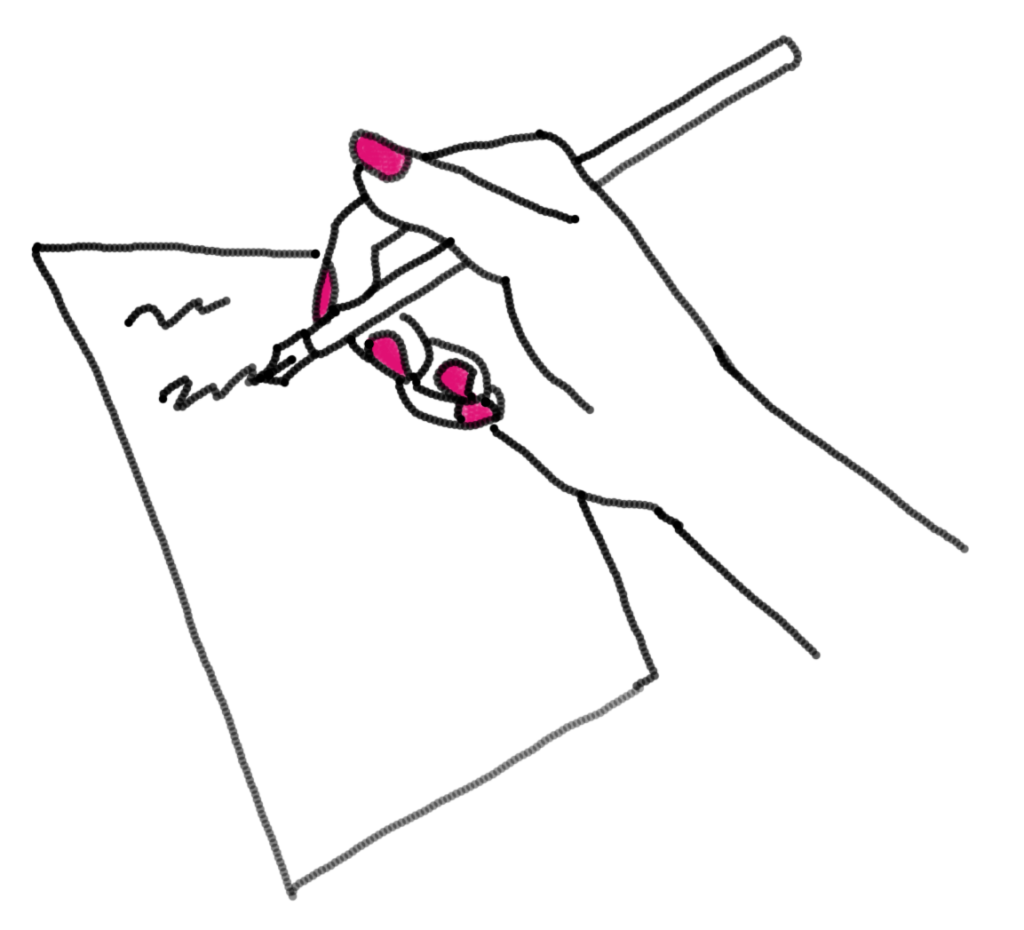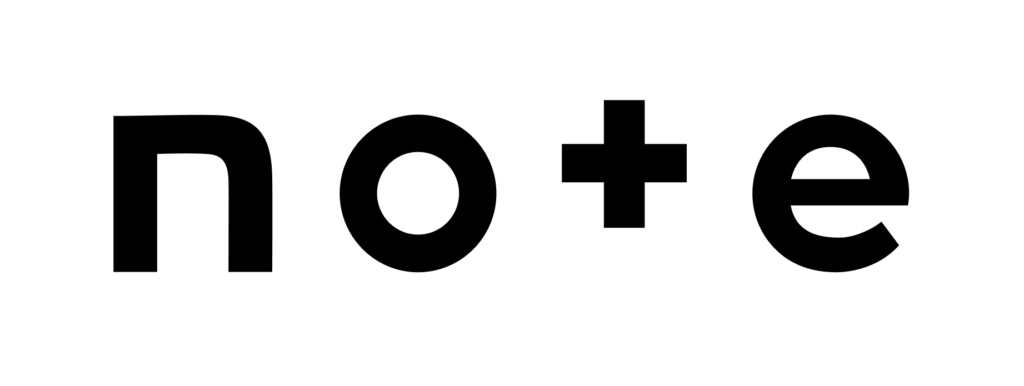「君はフィクションに向いていないよ」
恥ずかしい話になるが、素直に書いてみる。
私はもともと小説家志望だった。
文学賞の選考はいつも最初だけは通るけど、結局いつも最終選考では選ばれないということを繰り返していた。いつもいつもある程度進んでから必ず落ちるので、最終の選考委員との相性が悪いだけとどこかで思ったりもしていた。
ある日、編集者の方に「表現力も話の進め方自体も上手だけど、ストーリーが致命的に面白くない」と言われ、そんなはずはないと思っていたけれど、また別の出版社でも別の編集者の方から似たようなことを言われた。
こういう企画なら本を書いてくれたら出せるよ、とまで譲歩のような提案もいただいたが、それならいいですと断ってしまった。
そして最後にこう言われた。
「君はフィクションに向いていないよ。
それよりは、ノンフィクション作家として自分の経験したことを書くのがいいんじゃない」


なんとなく、自分でもそれは感じ始めていた頃だったので、そう言われたことは腑に落ちた。だけど、悔しかったし、納得はできなかった。私は小説家になるんだと、なぜか信じて疑わないまま。
幸いなことに「書いたら見せてよ」と言ってくれる編集者の方々には恵まれていたので、何度も見せ続けたが、話はまとまってるのにピンとこないと言われるなどして、自然と自分から遠のいてしまった。プロがせっかく見てくれてるのにこれなら、だめだ。もう、書けない。
なのに書くことには執着していたので、自然とライターになった。
創作とは距離があるが、情報を実際に見たり聞いたりして文章にしていく仕事は、読まれることが多い充実感のある仕事で、コツコツとやるのはとても楽しい。
特に出版社で毎日文字を紡いでいた頃は、その環境がありがたくて仕方がなかった。
その中でも引っかかり続ける感情には抗えず、周囲にはぽろぽろと漏らし続けていた。すると先週、10年来の友人にこう言われた。
「僕も君は文章はうまいなと思ってるけど、フィクションには向いていないと思うよ」
あ、編集者だけじゃない。
友人さえ、そう思っているのか。
ちょっとショックだった。でも正直に言ってくれることには、ありがたいなと素直に思った。
26歳、既婚。
いい加減もっと地に足つけろと言われてもおかしくないけど、まだ必死に夢にしがみついている。
お金になるわけじゃないけれど、劇団の脚本を書いたり。小銭稼ぎをかねて、恋愛ゲームのシナリオを書いたり。なんとなくやっぱり近い仕事はやめずに続いている。
そして今、結局書くことは続けてしまっている。書き続けている。ほとんどの仕事はこんなにもイヤイヤ言ってるのに、個人的な創作だけは無意識に続けている。
できるところまでもうちょっと頑張りたい。あともう少しでいいから、もうちょっとだけ、やらせて。誰にことわりをいれてるんだろう、でもずっとそう思っている。
ノンフィクション作家は、ライターの仕事に近い。私は食わず嫌いをしているだけなのかもしれない。もうちょっと、編集者の方の提案に耳を傾けた方がいいのかもしれない。
したくない仕事でも、向いている仕事はある。
したい仕事でも、向いていない仕事はある。
残酷だけどそれが現実なので、私はもうちょっとそれに向き合ってみる。
でないと、今毎日ライターの仕事依頼をもらうたびに、私は何かに嘘をついているような罪悪感と戦い続けてしまうから。