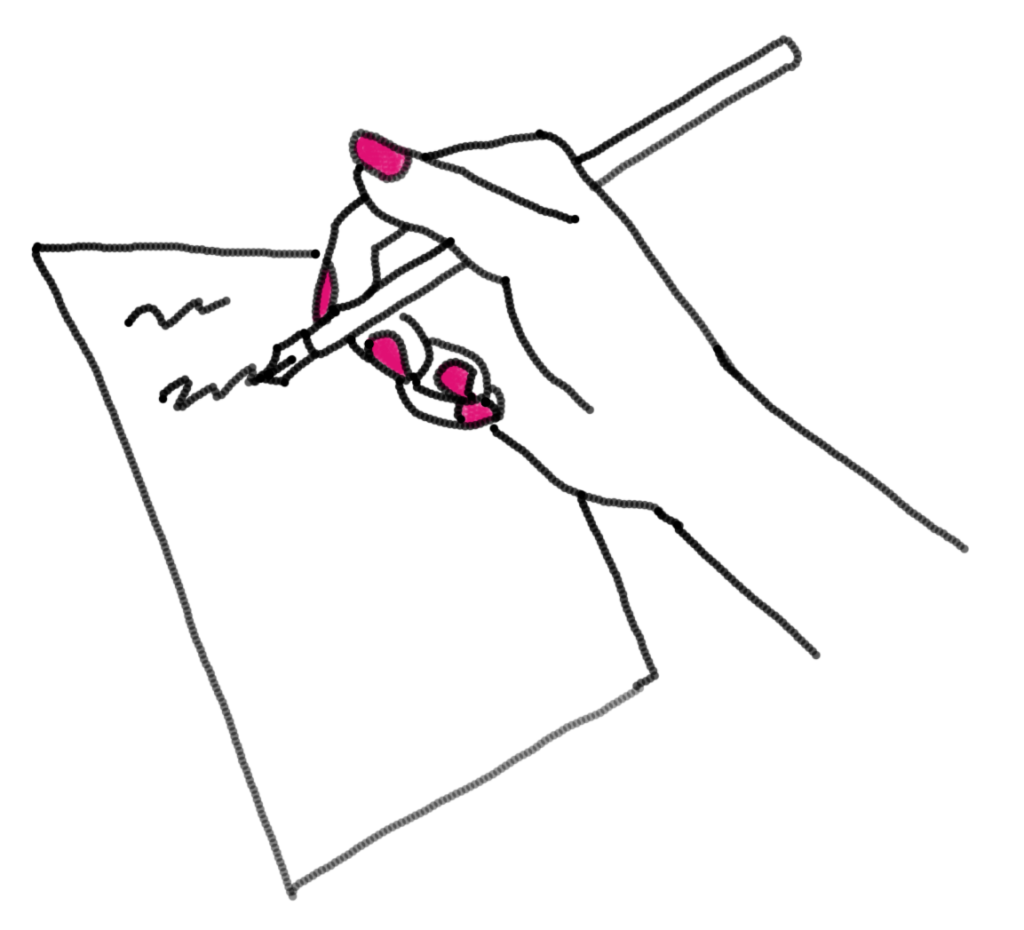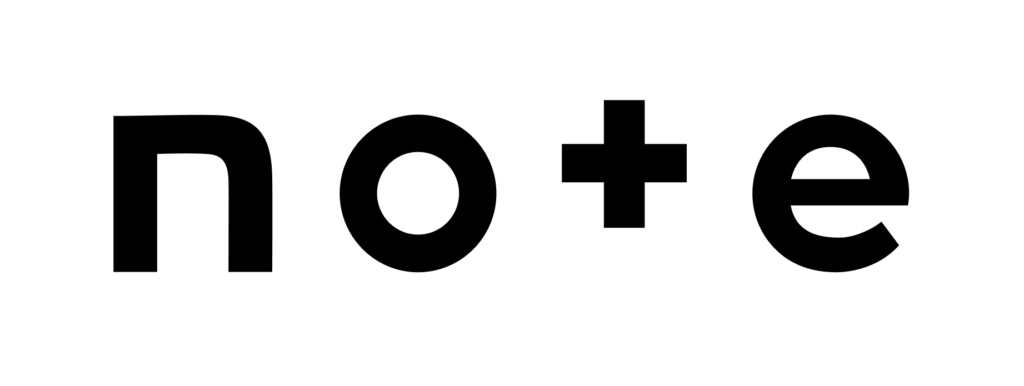わたしの好きなひとりの後輩
息をするという意味での生きる、ってのは、病気やらなんやらしない限りは基本的にそんなに難しくないかもしれないけれど、生き続ける中で死にたくなる衝動に打ち勝って頑張って生きる、という意味では生きることって、多分とっても難しい。
きちんと死なずにたくましく生きている人間が多いこの世の中において、自殺をせずに生きることはなんだか当然のように思われがちだが、「自殺」って単語があるぐらい、人間は自ら死を選ぶことが出来る生き物なわけで、それを選ばずに生きるってのはやっぱりすごいことなわけだ。まったくもう、立派でござる。
いつかきちんと、(わたしがこれからもずっとちゃんと自殺への誘惑に打ち勝ち、きちんと生きてたら)このブログにでもちゃんと詳しく書こうと思う、ひとりの人間がいる。今日は、彼女に少しだけ触れたい。
わたしの高校時代から長い付き合いの彼女は、わたしの2つ年下で、様々な感情を凝縮してギュッと目をつぶりながら人生を歩んでいるような女の子だ。どんなことにも恐れずに突き進む変な勇気を持ち合わせながらも、いつも誰からも見放されてしまうかもしれないと不安感のような見えない敵といつも戦っていた。
彼女は頭が良いからこそ、自分が有名な何者なんかにはなれないという自覚をきちんとしていて、とても謙虚だった。本当は才能が溢れてたまらない彼女に、わたしは嫉妬すら覚えていたが、彼女は自分のその才能を『あんまり、いやほぼ無いんですわ』と信じて疑わぬ謙虚な人間だった。本当は、すっごくあったんだけれども。
人懐っこい彼女は、いつもヘラヘラと笑う。
悪い意味ではなく、かと言って良い意味でも無い。事実として彼女は、ヘラヘラと笑う。頭の回転が早く、教養もあるが、誰かを否定することは決してしない。誰かに否定的な意見をいうことも無い。何かを常に怖がり、まずそうな事態になると、ヘラヘラと笑ってやり過ごそうとする。それは彼女の癖であり、生き方だった。
ひとによっては、そんな態度は「無責任な野郎だ」と映るのだろうが、彼女にとって社会へのその態度は、彼女なりの最適解の態度だった。
事を荒立てずに、自分への敵を作りたくない、そんな心理の現れだったのだろうと思う。わたしはそんな穏やかに、どこかテキトーにやり過ごそうとする、そんな彼女の態度の意味をきちんと知った上で、彼女を好きだった。それはもう、たまらなく好きだった。人生で一番、可愛がった後輩だった。
日常生活において、彼女にはだらしない部分も幾分か正直いえば、あった。
でもそれに勝る、素直な笑顔というか、無条件な愛しいひとへの懐き方に、みんな基本的に嫌な気持ちはしなかったはずだった。彼女は周囲の人間に、まあ全員とは言わない、だけれど多くの人間に愛される人間だった。それは間違いのない事実だと、わたしは胸を張って言える。
彼女は半年ほど前に、自殺した。詳細は省く。
亡くなる4日前に会った彼女は元気そのものだった。
生き生きとしていて、恐れるものがいつもよりも少なそうに生きていた気がする。
今度ここに一緒にいこうね、などという約束などもした。
それでも、人間は死を選んだりする。止められなかったりする。
しばらく、わたしは人生で一番悲しみにくれた。
大学にもバイトにも、しばらくきちんと行けなかった。
たった四日前に会っているのになぜ、わたしは止められなかったのか。
病気や事故で亡くなる人間は、勿論悲しいけれど、まだ気持ちに整理が幾分かつく。時間をかけながら、でも誰を責めるでもなく(ときには明確に誰かを責められるが)、丁寧に順序を追って立ち直れる。
だが、自ら命を絶つ選択をされた時、周囲の人間は整理がいつまでもつかなかったりする。現に今、わたしは未だ全くといって良いほど前に進んでいない。何も出来なかったのか、と自分を責め立てる。責め続けている。
その矛先は、明確にわたし自身へと向かう。
わたしが何もできなかった、わたしが、わたしが、わたしのせいで。
亡くなった直後はただただ悲しみにくれていたが、葬式に出席した後に、わたしは長期間幻聴に悩まされた。自分を責める気持ちも加速する。
彼女の、声がするのだ。部屋に一人でいるときに、斜め後ろから声がするのだ。
『ねえさん、聞いてくださいよォ』
そのいつもの口調で、彼女はわたしに話しかける。
幻聴だとわかっていても、わたしは返事をしてしまう。
当時、わたしの周囲の人間は、わたしがこのまま後追い自殺する、と本当に思ったようだ。現に、ぷっつりと連絡がつかなくなってしまったわたしの部屋に、マンションの高い階だったにも関わらず友人がベランダから侵入してきたほどだった。(すごく感謝している)わたしは幻聴を相談していた精神科にもらった睡眠薬の飲み過ぎで、朦朧としていた。
幻聴は正直、今も時々気を抜いていると、キッチンに立っている時なんかに聞こえたりする。わたしは、自分自身を責めることをやめられない。
あー、このままじゃまずい、どうにかしなきゃなァ
彼女のためにも、どうにかしたいなァ
そんな毎日彼女のことを考えてしまう日々の中で、今日、わたしは何気なく本棚から一冊の本を取り出した。
彼女が、わたしが去年病気で入院している時に、お見舞いで買ってきて届けてくれた本である。
『わたしの好きな本なんですよ、ねえさん読んでくださいよ』
そう言われながら有り難く頂戴したが、入院時は手術後の痛みなどで読むことは出来なかった。そのまま持って帰り、本棚になにげなく仕舞っていた本だった。
今日、はじめてその本を開いた。
まず本に触れるだけで、手の震えが止まらなかった。
次にページを開く。瞬間的に、涙が溢れた。
結果、1ページも読み進められなかった。
それでも、わたしは少しずつ本を読み進めてみようと今、思っている。彼女の好きだったという本は是非とも読みたいのだ、でもこれを読み終えてしまうと、なにかがひとつ終わるような変な焦りがある。なんとも言いがたい、不思議な読みたくない気持ちに強く阻まれる。だから、焦らずに読もうと思う。
そんな彼女がくれた本を読み進められることは出来ずにいるが、才能があふれる彼女自身が書いた文章や同人誌へのエッセイ、ブログなんかは何度も読み返している。わたしはいつも、彼女の何かをひとつでもわかってあげられただろうか、より添えていたのだろうかと考える。天国で再会する日まで、その事実を問うことはできやしない。けれど、天国出会えたなら、真っ先に尋ねたいのは、わたしは貴女にとって良い先輩であれただろうか、ということだ。そして、何も出来なくてごめんなさい、と土下座したいのだ。
死を選び、実行するとき、きっと彼女は孤独のなかにいたのだろう。
真っ暗な、救いようのない不安感のなかで押しつぶされそうになっていたのだろう。
わたしはその孤独の瞬間も、きっと遠く離れた場所でテレビを見ていたり普通に過ごしていたのだろう。
ほんとうに、彼女になにもできなかった。
そんな自分を責めつづけることはやめられなさそうなので、もうやめようとするのをやめちゃおう、と今日思った。
わたしはこの罪悪感と生きていく。決めたのだ。
わたしに出来なかったことは、事実としてあるのだ。
あのLINEをこう返していれば、あのときこう答えていれば、電話していれば。
そのベターだったのだろうという答えは尽きない。
幻聴も、まだしばらく消えないのかもしれない。
それでもいい、わたしは今は元気に大学に通っている。
生きることは、難しい。
自殺するという選択肢が容易に選べる現代で、わたしは生きるほうを選び続けることにとても難しさを感じている。
でもそんな時にこそ、彼女を思う。すると、彼女の声が聞こえてくる。
『ねえさん〜、ねえさんはしっかり生きてくださいよォ〜』
そのヘラヘラとした可愛い声が、わたしの耳に届く。ひとはこれを幻聴と言う、おまえまずいよ、と心配してくれる。
でもわたしは、わたしが生きることから逃げ出さないように、彼女が見ていてくれるんだろうと思うようにしている。もう、そう思いでもしないとしんどい。逃げちゃう。
少しずつ頻度が減っているこの幻聴が、いつかほんとうに聞こえなくなるのだと思う。そのときにわたしは、彼女のくれた本を読み終えることが出来るのかもしれない。
ひとがする自殺という選択を、わたしは良いとも悪いとも言えない。
でも少なくともただひとつ言えることがあるとするならば、自分は誰にも愛されていないと感じていたとしても、愛していた周りはもっと苦しむんだということを、ひとつ覚えておくべきだと思う。
今日も彼女が、様々な噂や事柄から遠くはなれて、静かに安らかに眠っていますよう。ねえさんは、祈っています。今日も、生きています。